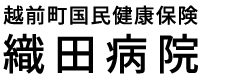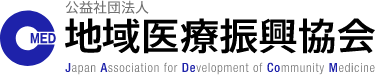臨床検査室のご案内
臨床検査は、一般的に生理検査と検体検査とに大きく二つに分類されます。生理検査は、直接人体からの情報を分析するもので、心電図検査や呼吸機能検査、神経伝導検査などがあります。検体検査は患者さんから尿、血液、体腔液などの検体(材料)を採取し、それらを化学的に分析、形態学的に検査するものです。これらのデータは医師に提供され、病気の診断や治療に役立っています。
基本理念・基本方針
基本理念
丁寧・迅速・正確な臨床検査
基本方針
- 正確かつ迅速に検査情報の提供を行う
- 検査技術の習得、専門分野の高度な知識と技術の会得
- 他部署との協力体制を高め、診療支援に努める
- 検査業務の効率化とコスト削減に努める
- 安全管理の強化に努める
スタッフ
臨床検査室では、チーム医療の一員として患者さんへのよりよい医療の手助けになれるよう、迅速で正確な情報の提供を心掛けています。
臨床検査技師(常勤) 3名
臨床検査技師(非常勤) 1名
生理検査
1)標準12誘導心電図
心臓の活動に異常があるかどうかを調べる検査です。
不整脈・狭心症・心筋梗塞・心肥大・伝達障害などの有無とその種類を調べます。
2)ホルター心電図
携帯型心電計を装着し、日常生活の心電図を24時間記録する検査です。
不整脈の有無や頻度、薬の治療効果、自覚症状と心電図変化の関係を調べます。
3)負荷心電図
体を動かしたときに胸痛症状が出現する労作性狭心症などを心電図で調べます。
はじめに安静時の心電図を記録し、次に凸型の検査専用の二段の階段を昇降運動して心拍を上げ再度心電図記録し、運動(負荷)前後の心電図変化を判定する検査です。
4)ABI
両手両足の血圧を同時に測定し、血管の硬さや血液の流れの状態をみる検査です。
5)呼吸機能検査
肺の容積や弾力性・換気能力・気道の異常などを調べる検査です。
気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの診断に用いられます。
また、手術前検査としても行われます。
6)神経伝導検査
電気刺激が神経を伝わる速度を測定する検査で、網膜剥離や緑内障などの眼科疾患や動脈硬化の進行具合を調べます。
7)眼底検査
眼底の血管、網膜、神経を調べる検査で、網膜剥離や緑内障などの眼科疾患や動脈硬化の進行具合を調べます。
検体検査
1)生化学的検査
体内に含まれている血液中の酵素、蛋白質、糖質、脂質などの生化学成分について検査しています。
2)免疫学的検査
心疾患や甲状腺機能、B型肝炎やC型肝炎といった感染症に関わる抗原や抗体、腫瘍マーカーなどについての検査をしています。
3)血液学的検査
個々の赤血球・白血球・血小板の数や大きさ、赤血球に含まれているヘモグロビン量を測定し異常がないか、また顕微鏡で観察し形態的変化がないかを確認します。
これらの検査値や検査所見は、貧血症、多血症、出血、炎症、造血器主腫瘍などのスクリーングや疾患治療に対する治療効果のモニタリングとして重要な検査です。
4)凝固検査
血液が固まることを凝固、それを溶かすことを線溶といい、それらの値を測定します。
血液・線溶の値は正常ではバランスがとれていますが、出血症状や血栓があるとそのバランスが崩れるので変化がないかを確認します。これらの検査値は、出血リスクの有無やワーファリンやヘパリンなどの抗凝固薬の効果のモニタリングや評価に必要不可欠です。
5)尿検査
尿中に蛋白や潜血・糖などが出ていないかについて判定量的に調べる検査です。
また顕微鏡で観察し、細菌の有無や細胞の形態・数に異常がないかを確認します。
尿路感染症や腎臓・膀胱の疾患を診断するのに必要な検査です。
6)輸血検査
輸血を行う上で、ABO式、Rh(D)式血液型と交差適合試験をしています。